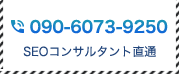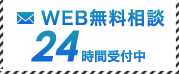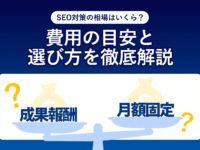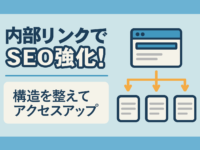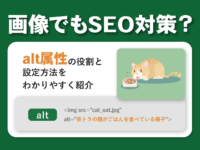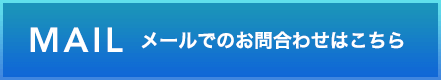SEO対策コラム
SEO対策に関するコラムです。
- 名古屋SEO対策CatworkSEO
- SEO対策コラム
- SEO対策はクローラー理解から!仕組みを学んでアクセスアップ
SEO対策はクローラー理解から!仕組みを学んでアクセスアップ
2025.04.7
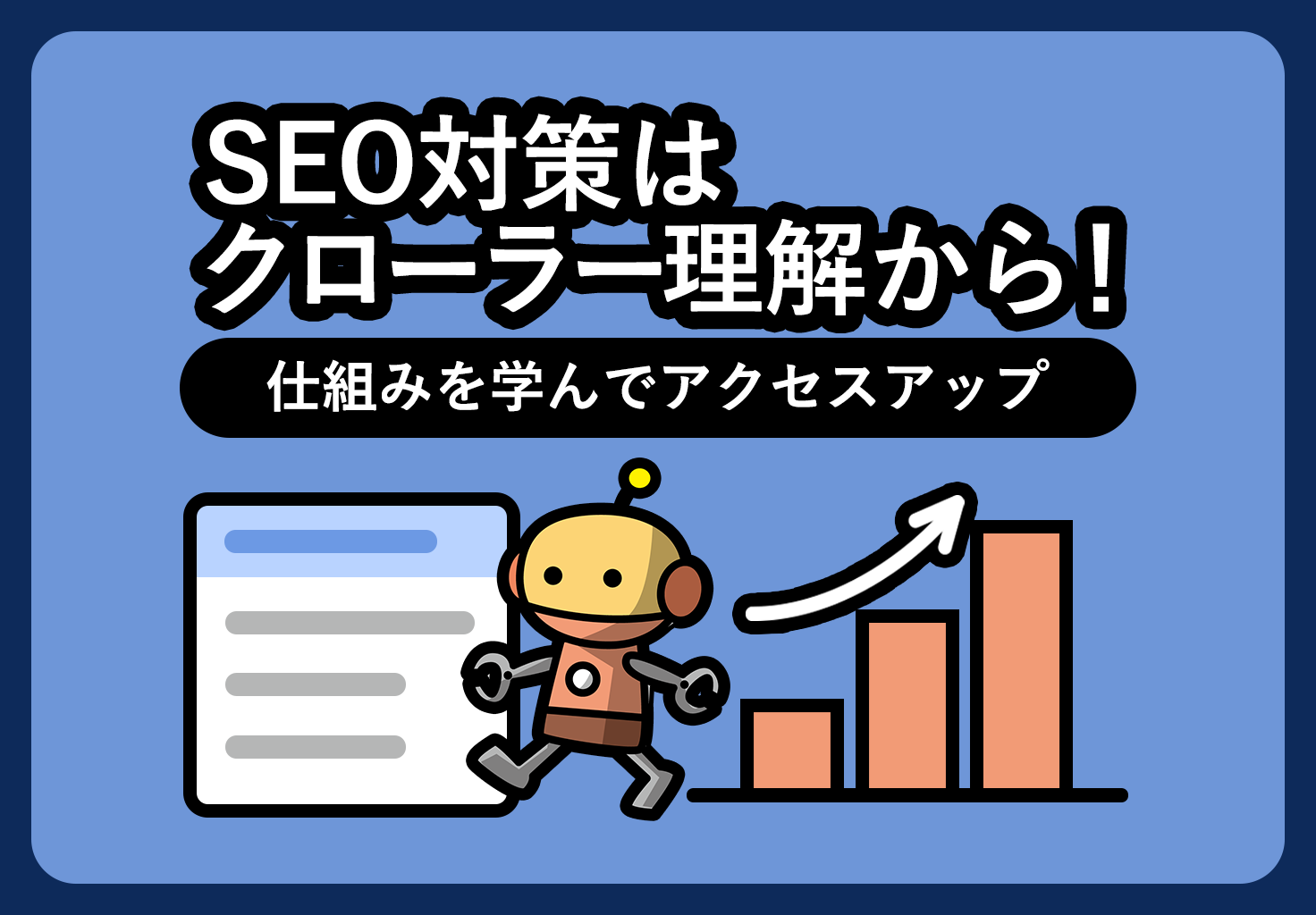
Webサイトのアクセスを増やすために欠かせないのが「SEO対策」。しかし、どれだけ良いコンテンツを用意しても、検索エンジンに正しく認識されなければ意味がありません。
その鍵を握るのが「クローラー」の存在です。クローラーとは、検索エンジンがWeb上の情報を収集するためのロボットのようなもの。この記事では、クローラーの基本的な仕組みや動作原理をわかりやすく解説しながら、SEO対策にどのように活かせるのかを紹介します。
検索順位を上げたい方、アクセス数を伸ばしたい方は、ぜひ最後までご覧ください!
この記事を読んでわかること
- クローラーの役割と仕組み
- 検索エンジンがサイトを評価する流れ
- クローラーに好かれるサイト構造のポイント
- robots.txtやサイトマップの活用法
- SEO対策におけるクローラー最適化の具体的な方法
目次
- 1. SEO対策とクローラーの関係とは?
- 1-1. クローラーは検索エンジンの情報収集ロボット
- 1-2. クローラーに見つけられなければ、検索結果に表示されない
- 1-3. SEO対策=クローラー最適化でもある
- 2. そもそもクローラーとは何か?役割と基本動作を解説
- 2-1. クローラーとは「Webの巡回ロボット」
- 2-2. クローラーの主な役割は3つ
- 2-3. クローラーの動き方:リンクを辿って巡回
- 3. Googleのクローラー「Googlebot」の仕組みとは?
- 3-1. Googlebotとは?
- 3-2. Googlebotの巡回の仕組み
- 3-3. 巡回の頻度や範囲はコントロール可能
- 4. クロール、インデックス、ランキングの流れを理解しよう
- 4-1. ステップ1:クロール(Crawl)
- 4-2. ステップ2:インデックス(Index)
- 4-3. ステップ3:ランキング(Rank)
- 5. クローラーが巡回しやすいサイト構造のポイント
- 5-1. 内部リンクはわかりやすく整理する
- 5-2. フラットでシンプルな階層構造を意識する
- 5-3. URL設計もクローラーに優しく
- 5-4. JavaScript依存のコンテンツに注意
- 6. robots.txtとmetaタグでクロールを最適化する方法
- 6-1. robots.txtとは?クローラーの通行止め指示書
- 6-2. metaタグによるクロール・インデックス制御
- 6-3. 適切な制御でクロールの効率化を
- 7. サイトマップ(XML)はなぜ重要?SEOへの影響と作成方法
- 7-1. サイトマップ(XML)とは?
- 7-2. SEOにおけるサイトマップの効果
- 7-3. サイトマップの作成と送信方法
- 8. 重複コンテンツとクロールの無駄遣いに注意!
- 8-1. 重複コンテンツってなに?
- 8-2. なぜSEOに良くないの?
- 8-3. 重複を減らすためのポイント
- 9. モバイル対応と表示速度もクローラーに影響する理由
- 9-1. モバイル対応は必須の時代
- 9-2. 表示速度が遅いと離脱されやすい
- 9-3. モバイル対応+表示速度はセットで考えよう
- 10. まとめ:クローラーの仕組みを活かしたSEO対策でアクセスを伸ばそう
- 10-1. クローラーの基本をおさらい
- 10-2. SEO対策に活かす具体的なポイント
- 10-3. 地道な改善がアクセスアップに繋がる
SEO対策とクローラーの関係とは?
検索エンジンで上位に表示されるためには「SEO対策」が不可欠です。そして、そのSEO対策の土台にあるのが「クローラー」の存在。ここでは、クローラーとSEOの関係性について詳しく解説していきます。
クローラーは検索エンジンの情報収集ロボット
クローラーとは、Googleなどの検索エンジンがインターネット上の情報を自動で巡回・収集するプログラムのことです。Googleでは「Googlebot」という名前のクローラーが使われており、世界中のWebサイトを巡って新しい情報を見つけ出し、検索エンジンにインデックス(登録)しています。
クローラーに見つけられなければ、検索結果に表示されない
どれだけ質の高いコンテンツを作っても、クローラーにページが見つけられなければ検索結果に表示されません。つまり、ユーザーの目にも触れないということ。SEO対策の第一歩は、まず「クローラーに正しく見つけてもらうこと」です。
SEO対策=クローラー最適化でもある
SEO対策というと「キーワード選定」や「タイトルの工夫」に注目しがちですが、実は「クローラーが巡回しやすいサイト構造を作ること」も重要な対策のひとつです。サイトの構造が複雑だったり、不要にクローラーのアクセスを制限していたりすると、ページがインデックスされにくくなり、結果的にSEO効果が薄れてしまいます。
このように、クローラーの理解はSEO対策の土台となる部分です。次のセクションでは、クローラーの基本的な仕組みについてさらに深掘りしていきます。
そもそもクローラーとは何か?役割と基本動作を解説
SEO対策において欠かせない存在である「クローラー」。その名前は聞いたことがあっても、実際にどんな働きをしているのか知らない人も多いかもしれません。このセクションでは、クローラーの基本的な役割と動作の流れについてわかりやすく解説します。
クローラーとは「Webの巡回ロボット」
クローラー(Crawler)とは、検索エンジンがWeb上の情報を収集するために使う自動プログラムです。Webページのリンクをたどりながら、次々とページを巡回(クロール)していくことから、「クローラー」または「スパイダー」とも呼ばれます。
たとえばGoogleでは「Googlebot」というクローラーが使われており、世界中のWebサイトを日々巡回しています。
クローラーの主な役割は3つ
クローラーの働きは大きく分けて以下の3つです。
- 情報収集(クロール)
クローラーがページを訪れ、HTMLなどの情報を取得します。 - インデックス登録
収集した情報を検索エンジンのデータベースに保存します。これを「インデックス」と呼びます。 - 検索順位決定(ランキング)へのデータ提供
インデックスされた情報は、検索クエリに応じて表示される順位の評価材料になります。
クローラーの動き方:リンクを辿って巡回
クローラーはリンクを手がかりに次々とページを巡っていきます。たとえば、トップページにリンクされたページからさらに内部ページへと移動して情報を収集します。このため、リンク構造が整理されていないと、重要なページが見逃されることもあります。
クローラーは単なる情報収集ロボットではなく、検索結果に表示されるための「入口」です。次のセクションでは、Googleの代表的なクローラー「Googlebot」について詳しく見ていきましょう。
Googleのクローラー「Googlebot」の仕組みとは?
検索エンジンの中でも圧倒的なシェアを誇るGoogle。そのGoogleが使用しているクローラーが「Googlebot(グーグルボット)」です。この章では、GooglebotがどのようにWebサイトを巡回し、どのように情報を処理しているのかを解説します。
Googlebotとは?
Googlebotは、Googleの検索エンジン専用のクローラーです。Webサイト上のリンクを自動でたどり、ページのHTML情報やコンテンツを収集し、それをGoogleの検索インデックスに登録する役割を担っています。
一口にGooglebotといっても、いくつかの種類があり、PC向けページを巡回する「Googlebot Desktop」と、スマホ向けページを巡回する「Googlebot Smartphone」があります。現在は主にモバイル版が優先されており、モバイルファーストインデックスという仕組みにより、スマホ版の内容が評価の基準となっています。
Googlebotの巡回の仕組み
Googlebotはまず、以前にクロールしたページや、サイトマップに登録されたURL、外部リンクなどを起点に巡回を始めます。以下のような手順で動作します。
- クロール対象のURLリストを作成
Googleのシステムは、巡回すべきURLをリストアップします。 - 優先順位を決定
新しいページや更新頻度の高いページが優先されやすくなります。 - アクセスと取得
実際にWebサイトへアクセスし、HTMLデータを取得します。 - インデックス登録処理へ
取得した情報はGoogleのインデックスに送られ、分析・登録されます。
巡回の頻度や範囲はコントロール可能
Googlebotの巡回頻度は、サイトの更新頻度や信頼性によって異なります。また、robots.txtファイルやメタタグで、クロールさせたいページ・させたくないページをコントロールすることも可能です。これにより、SEOにとって不要なページがインデックスされないように調整できます。
Googlebotの仕組みを理解することで、検索エンジンに「正しく評価されるサイト」を設計できるようになります。次は、クロールからインデックス、そしてランキングまでの全体の流れを見ていきましょう。
クロール、インデックス、ランキングの流れを理解しよう
SEO対策を考える上で、「クローラーに見つけてもらう」だけでは不十分です。クローラーがページを巡回したあと、検索結果に反映されるまでには「クロール → インデックス → ランキング」という一連のプロセスが存在します。この流れを正しく理解することで、より効果的なSEO施策を行うことができます。
ステップ1:クロール(Crawl)
クロールとは、GooglebotなどのクローラーがWebページにアクセスし、ページの内容を読み取るプロセスです。この段階でHTMLの構造、テキスト、画像、リンクなどの情報を取得します。
重要なのは、クローラーにアクセスしてもらえるように設計されているかどうかです。リンク構造が整っていなかったり、robots.txtで制限されていたりすると、クロールされない可能性があります。
ステップ2:インデックス(Index)
クローラーが取得した情報は、Googleのデータベースに登録されます。これを「インデックス」と呼びます。インデックスされていないページは、いくら優れたコンテンツでも検索結果には表示されません。
正しくインデックスされるためには、HTML構造の最適化や、サイトマップの送信が有効です。
ステップ3:ランキング(Rank)
インデックスされた膨大なWebページの中から、Googleはユーザーの検索意図に最も合致するページを選び、ランキング(順位付け)します。このとき、コンテンツの質、ユーザーの利便性、モバイル対応、表示速度、外部からの評価(被リンク)など、200以上の評価基準が使われると言われています。
この3ステップを理解すれば、単に「検索される」だけでなく、「上位に表示される」ための視点が身につきます。次のセクションでは、クローラーが巡回しやすいサイト構造について解説します。
クローラーが巡回しやすいサイト構造のポイント
クローラーにとってアクセスしやすいサイト構造は、SEOの基本であり重要な土台です。どれだけ質の高いコンテンツを用意しても、クローラーがスムーズに巡回できなければ、検索結果に表示されることはありません。この章では、クローラーが迷わず巡回できるサイトを作るためのポイントを紹介します。
内部リンクはわかりやすく整理する
クローラーはリンクをたどってページを巡回します。そのため、内部リンクが適切に張られていることは非常に重要です。トップページから重要な下層ページへ数クリック以内で到達できるようにし、カテゴリ構造やパンくずリストなどで全体の流れを整理しましょう。
フラットでシンプルな階層構造を意識する
サイトの階層が深すぎると、クローラーが奥までたどり着けないことがあります。理想は**3階層以内(トップ → カテゴリ → 記事ページ)**におさめること。複雑な構造よりも、誰が見ても分かりやすいサイト構成を目指すことが、結果的にクローラーにも優しいサイトになります。
URL設計もクローラーに優しく
URLが長すぎたり、意味のない文字列(例:example.com/page?id=12345)ばかりだと、クローラーはそのページの内容を正しく理解しにくくなります。人間にも理解しやすいシンプルで論理的なURLを設定しましょう。例:/blog/seo-crawler/
JavaScript依存のコンテンツに注意
JavaScriptで生成されるコンテンツやリンクは、クローラーが正しく認識できないことがあります。重要な情報やリンクは、HTML上に直接記述するようにしましょう。必要に応じて、Google Search Console の「URL検査ツール」で正しく読み込まれているかを確認するのも有効です。
クローラーにとって巡回しやすいサイトは、ユーザーにとっても使いやすいサイトです。次は、クロールの可否を設定できる「robots.txt」やmetaタグについて詳しく解説していきます。
robots.txtとmetaタグでクロールを最適化する方法
クローラーにとって巡回しやすいサイト構造を作ることは大切ですが、「どのページをクロールさせるか/させないか」を制御することも、SEO対策において非常に重要です。無駄なページをクロールさせず、重要なページに集中してもらうために使われるのが「robots.txt」と「metaタグ」です。
robots.txtとは?クローラーの通行止め指示書
robots.txt(ロボッツ・テキスト)は、Webサイトのルートディレクトリに設置するファイルで、クローラーに対して特定のページやディレクトリへのアクセスを禁止する指示を出すためのものです。
例:
makefileUser-agent: *
Disallow: /admin/
Disallow: /private/
上記はすべてのクローラーに対し、「/admin/」「/private/」ディレクトリ内は巡回しないように指示する内容です。
※注意:robots.txtで禁止しても、インデックスされる場合があるため、インデックスを完全に防ぎたい場合はmetaタグを併用します。
metaタグによるクロール・インデックス制御
HTMLの<head>内に設置するmetaタグでも、クローラーの挙動を制御できます。特に使われるのは「robots」タグです。
例:
html<meta name="robots" content="noindex, nofollow">
これは、「このページをインデックスしない」「このページ内のリンクもたどらない」という意味になります。管理画面や重複コンテンツなど、検索結果に出す必要がないページに使うと効果的です。
適切な制御でクロールの効率化を
クロールの上限(クロールバジェット)は限られているため、不要なページを巡回させると、本当にインデックスしてほしいページのクロールが遅れる可能性があります。robots.txtとmetaタグを使って、重要なページにクローラーのリソースを集中させましょう。
次は、クローラーにとって道案内となる「サイトマップ(XML)」について詳しく解説します。
サイトマップ(XML)はなぜ重要?SEOへの影響と作成方法
クローラーにとっての「道しるべ」となるのが、XMLサイトマップです。これは、Webサイト上のどのページをクロールしてほしいかを検索エンジンに明確に伝えるためのファイルであり、SEOの基本ツールのひとつです。この章では、XMLサイトマップの役割とSEOへの効果、そして作成・送信方法について解説します。
サイトマップ(XML)とは?
XMLサイトマップは、サイト内のURLをリスト化したファイルです。クローラーに対し、「このページも忘れずに見に来てください」と伝える役割を持ちます。たとえば以下のような構造です:
xml<url>
<loc>https://example.com/page1</loc>
<lastmod>2025-03-01</lastmod>
<priority>0.8</priority>
</url>
これにより、新しいページや更新されたページを優先的にクローラーが認識できるようになります。
SEOにおけるサイトマップの効果
- ページの発見性向上:内部リンクが届きにくいページでも、サイトマップに記載すればクロール対象になります。
- 更新状況の通知:
<lastmod>タグを使うことで、コンテンツの更新タイミングをGoogleに伝えられます。 - クロール効率の改善:クローラーが無駄な巡回を避け、重要なページに素早くアクセスできるようになります。
特に、大規模サイトや記事数が多いブログ、ECサイトには欠かせない要素です。
サイトマップの作成と送信方法
WordPressであれば、「Yoast SEO」や「All in One SEO」などのプラグインで自動生成できます。静的サイトの場合は、オンラインジェネレーターや手動で作成する方法もあります。
作成後は、Google Search Consoleに登録して送信しましょう。
送信手順は簡単で、「サイトマップ」メニューから /sitemap.xml などのパスを入力するだけです。
クローラーに確実にページを見つけてもらうためにも、サイトマップの活用は必須です。次は、SEOの落とし穴になりがちな「重複コンテンツとクロールの無駄遣い」について見ていきましょう。
重複コンテンツとクロールの無駄遣いに注意!
せっかく良いコンテンツを作っても、同じようなページがたくさんあると、検索エンジンにうまく伝わらないことがあります。これを「重複コンテンツ」といいます。さらに、それが原因でクローラーが無駄にページを見回ってしまい、大事なページが見逃されることもあるんです。
重複コンテンツってなに?
重複コンテンツとは、中身がほとんど同じようなページが複数ある状態のことです。たとえば:
- URLにパラメータがついたページ(例:
?id=123など) - 「https」と「http」、「wwwあり」と「なし」のページが両方ある
- 印刷用ページやブログのタグページなど、同じ内容を見せている別のページ
こうしたページがたくさんあると、Googleなどのクローラーは「どれが本物?」と迷ってしまいます。
なぜSEOに良くないの?
検索エンジンは、1つのサイトに使える「巡回(クロール)できる量」がある程度決まっています。これをクロールバジェットと呼びます。
重複コンテンツが多いと、クローラーが本当に見てほしいページにたどり着く前に疲れてしまうことになります。
また、似たようなページが多すぎると、どのページを検索結果に出せばいいのかわからず、すべてのページの評価が下がってしまうこともあります。
重複を減らすためのポイント
初心者でもできる対策は次のとおりです:
- 正しいページを「これが本物だよ」と伝える
→ サイトのコードに「canonical(カノニカル)タグ」を使います(プラグインで対応できる場合もあります) - URLのルールを統一する
→ 「httpsで統一する」「wwwなしにする」などを設定します(サーバーやCMS側でできます) - いらないページはクローラーに見せない
→ 管理画面やプリント用ページなど、検索に出す必要のないページは「見なくていいよ」と設定できます(robots.txtやmetaタグ)
| 項目 | 重複コンテンツがある状態 | canonicalタグで正規化した状態 |
|---|---|---|
| 検索エンジンの評価 | 複数のページに分散される | 正規ページに評価が集まる |
| インデックス状況 | 似たようなページが複数登録される可能性あり | 必要なページだけが明確に登録される |
| 検索順位 | 順位が上がりにくい(評価が分散するため) | 正規ページの順位が上がりやすい |
| クローラーの巡回効率 | 無駄なページを何度も巡回する | 重要ページに巡回が集中する |
| ユーザーへの影響 | 同じようなページが検索に出て混乱しやすい | 検索結果が整理されて見やすくなる |
| 対策方法 | 特になし | canonicalタグで「このページが本物」と伝える |
重複コンテンツを減らすことで、クローラーは効率よく巡回できるようになり、本当に見てほしいページが検索結果に出やすくなります。
次は、モバイル対応や表示速度がSEOにどんな影響を与えるのか、詳しく見ていきましょう。
モバイル対応と表示速度もクローラーに影響する理由
クローラーがどのページを巡回して、検索結果に表示するかを決めるとき、「モバイル対応」と「ページの表示速度」も大きなポイントになります。
どちらもユーザーにとっての「使いやすさ」に関わる部分なので、検索エンジンもとても重視しています。
モバイル対応は必須の時代
いまや多くの人がスマホでインターネットを見ています。そのためGoogleも、「スマホで見やすいサイトかどうか」をとても大事にしています。
実はGoogleのクローラーも、今はスマホ用のページを見に来るのが基本です(これをモバイルファーストインデックスといいます)。
つまり、スマホで見づらいサイトだと、クローラーがうまく情報を読み取れなかったり、評価が下がったりしてしまいます。
対策のポイント:
- スマホでも文字が読めるサイズにする
- メニューやボタンがタップしやすいか確認する
- 画面が崩れないようにレスポンシブ対応をする
表示速度が遅いと離脱されやすい
ページがなかなか開かないと、ユーザーはイライラしてすぐに離れてしまいますよね。クローラーも同じで、表示速度が遅いと巡回しづらくなることがあります。
さらにGoogleは、「表示速度が速い=ユーザーに優しい」と判断して、検索順位にも影響を与えています。
表示速度改善のコツ:
- 画像サイズを適切に圧縮する
- 不要なプラグインを減らす
- JavaScriptやCSSの読み込みを最適化する(プラグインで対応可)
モバイル対応+表示速度はセットで考えよう
「スマホで見やすい」「すぐ表示される」この2つがそろっていると、クローラーにも評価されやすくなり、ユーザー満足度も上がります。 SEO対策としてはもちろん、訪問者にとっても優しいサイトになるという、一石二鳥の効果があります。
次は、これまでの内容をふまえて、クローラーの仕組みを活かしたSEO対策のまとめに入っていきましょう!
まとめ:クローラーの仕組みを活かしたSEO対策でアクセスを伸ばそう
ここまで、クローラーの働きや仕組み、そしてSEOとの関係について、さまざまな視点から解説してきました。最後に、ポイントをおさらいしながら、どのようにSEO対策に活かしていけばいいのかをまとめていきます。
クローラーの基本をおさらい
- クローラーは検索エンジンの情報収集ロボット
- ページを巡回(クロール)し、データベースに登録(インデックス)する
- インデックスされた情報をもとに検索順位(ランキング)が決まる
この一連の流れを理解することで、検索結果に表示されるまでの仕組みがよくわかったと思います。
SEO対策に活かす具体的なポイント
- 巡回しやすいサイト構造を作る
→ 内部リンクやカテゴリを整理して、クローラーが迷わないようにする - robots.txtやmetaタグで無駄なクロールを防ぐ
→ 見せなくていいページはあらかじめ制御する - サイトマップを使ってページの存在を伝える
→ クローラーに「このページを見てほしい」と案内できる - 重複コンテンツを減らして評価を集中させる
→ 同じ内容のページが複数あると、クローラーも混乱します - モバイル対応&表示速度を最適化する
→ ユーザーにもクローラーにもやさしいサイトづくりを意識する
地道な改善がアクセスアップに繋がる
クローラー対策=テクニカルな話、と思われがちですが、実はユーザーのための使いやすいサイトを作ることと大きく重なっています。ひとつひとつ丁寧に対策を進めることで、検索エンジンからの評価も高まり、結果的にアクセス数やお問い合わせ、売上のアップにもつながっていきます。
クローラーの仕組みを味方につけて、あなたのサイトをもっと見つけてもらえるようにしていきましょう!
SEO対策に関する名古屋Catworkへのお問合わせ
まずは無料のWEB戦略相談で御社の状況をヒアリングし、
最適なWEB戦略をご提案致します。
お気軽にお問合わせ下さい。